
オフィスの清掃は、業務を円滑かつ快適に行うために欠かせないプロセスの1つです。しかし、清掃のルールは明確に定めないと、社員同士のトラブルのもとになりかねません。そこで本記事では、オフィス清掃の重要性やルールを作る際のポイントをまとめて紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
オフィスの清掃はなぜ重要?
オフィス清掃は企業にとって欠かせない取り組みです。一般的に従業員自身が行う社内清掃では、デスクやパソコン周り、床、エントランス、トイレ、給湯室といったスペースを対象に実施されます。こうした清掃活動は単なる習慣やマナーにとどまらず、国の基準に基づいた義務としても求められています。
厚生労働省が定める「建築物環境衛生管理基準」では、清掃や空気環境の調整、給排水の管理などを通じて職場環境を良好に維持することが努力義務として規定されているのです。とくに清掃に関しては「日常的に掃除を行うこと」「6か月以内ごとに大掃除を1回行うこと」と明確に示されています。
清掃は心身の健康にも寄与する
また、清掃には従業員の健康や心身に対するメリットも存在します。始業前に行う軽い清掃は、体を動かすきっかけとなり、デスクワーク中心の職場においては軽い運動効果が期待できます。さらに、ほこりやゴミを取り除くことで空気環境が改善され、社員の体調管理にも寄与することでしょう。
加えて、清潔な環境は社員の心理面にも好影響を与えます。整ったオフィスはモチベーション向上に直結し「整理・整頓・清潔・清掃」の4Sを徹底することで探し物の時間が減り、生産性向上にもつながります。
オフィスの清潔さは社外の評価にも直結する
さらに、オフィスの清潔さは社外からの評価にも直結します。とくに来訪者が目にするエントランスや会議室、応接室、トイレ、通路といった場所が清潔であることは、企業の印象を大きく左右します。明るく清潔な環境は信頼感や安心感を与え、取引先や顧客からの好印象にもつながるでしょう。
オフィスの清掃ルールを作る際のポイント
社内清掃を円滑に進めるためには、不公平感なく全社員が参加できるルール作りが重要とされています。
公平かつ負担の少ないルールを策定する
とくにフリーアドレスやハイブリッドワークを導入している企業では、当番の割り振りが難しくなるため、全社的に清掃の仕組みを整える工夫が求められます。
清掃を習慣化するためには曜日や時間をあらかじめ決め、掃除場所もエリアごとに分担する方法が有効です。清掃時間は15分程度に設定すると負担が少なく、継続しやすいでしょう。また、作業量に偏りが出ないよう担当場所をローテーション制にすることで、公平感を保てます。
清掃には社員全員で参加するのが望ましい
さらに、社内清掃は役職に関係なく全社員が参加することが望ましいです。管理職や上司が率先して取り組むことで、「オフィスの清潔は全員の責任」という意識が自然に浸透します。
営業職など出勤が不規則な社員に対しては、日程の調整や担当替えを柔軟に行うことで負担を軽減できます。加えて、清掃中は普段関わりの少ない社員同士が交流する場にもなり、コミュニケーションの活性化につながる点もメリットです。
オフィス清掃を外注するのも一つの手
社内での清掃が大きな負担となる場合は、オフィス清掃の専門業者に清掃を依頼するのも手です。オフィス清掃業者は、経験に基づいた効率的なオフィス清掃を行ってくれます。
これにより社員の清掃の負担が減れば、コア業務に集中することにもつながるでしょう。また、社員の清掃時間を給与に換算すると、業者に任せた方が安上がりなこともしばしばあります。
まとめ
オフィス清掃は、職場環境を快適に保つだけでなく、社員の健康維持やモチベーション向上、さらには企業の対外的な評価にも直結する重要な取り組みです。そのためには、不公平感をなくし全社員が協力できるルール作りが欠かせません。曜日や時間を決めて習慣化し、担当エリアをローテーション制にすることで負担を分散できます。また、役職に関係なく全員が参加することで「清潔は全員の責任」という意識が浸透し、社員同士のコミュニケーション促進にもつながります。一方で、清掃が大きな負担になる場合は専門業者に外注するという選択肢も有効です。自社に合ったルールを整備し、清潔で快適なオフィス環境を維持することが、働きやすさと生産性の向上に直結します。
 ダイオーズカバーオール
ダイオーズカバーオール 
 ダスキン
ダスキン 
 アーネスト
アーネスト 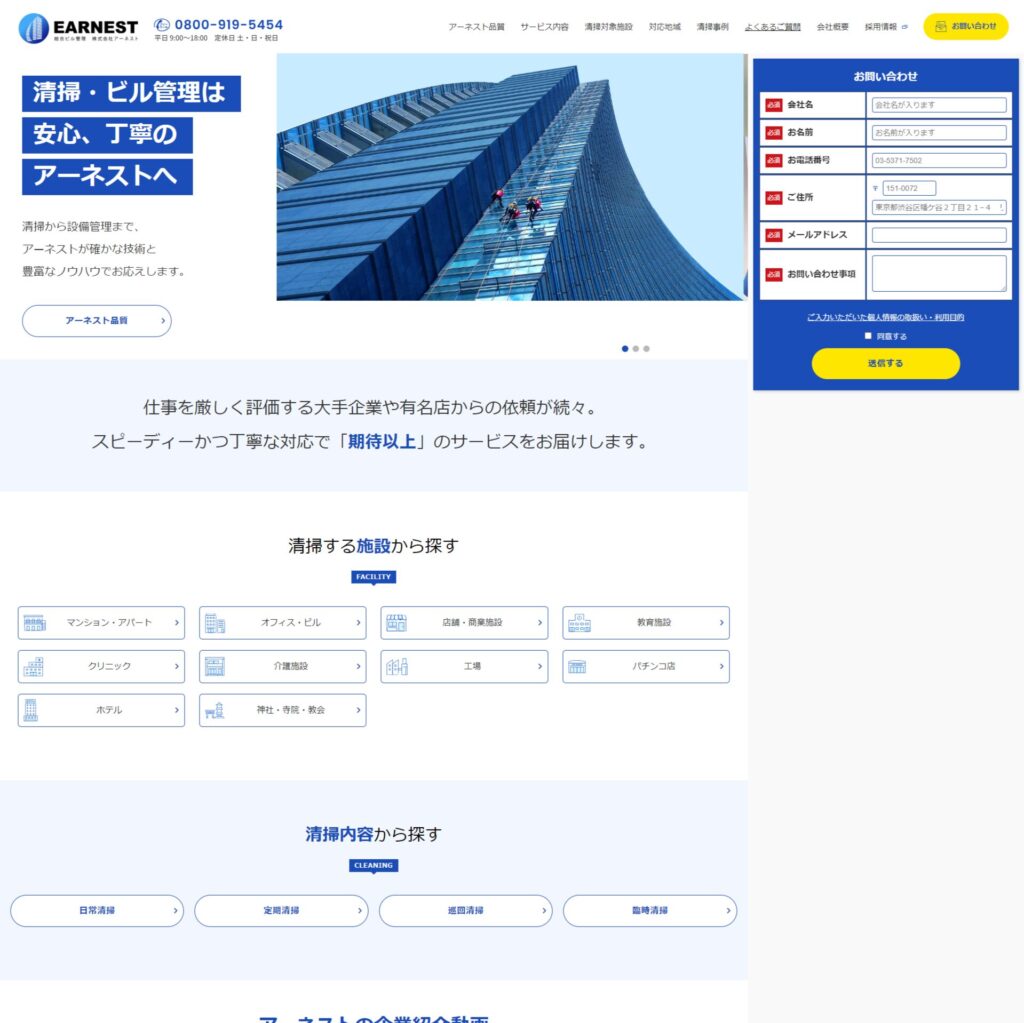
 ベアーズ
ベアーズ 
 アドバンスサービス
アドバンスサービス 





